なるほど豆知識
2015.1 vol.22 節分にみんなで豆をまこう!
年が明けたと思っていたら、あっという間に1月下旬です。
そこで、来月の行事「節分」について、今回はご紹介していきたいと思います!
「節分」ってなに?
![]()
古来より節分は、立春・立夏・立秋・立冬の前日を指し、季節の移り変わるときという意味があります。もともとは、1年に4回ある節分ですが現在では立春の前日だけを節分というようになっています。これは、特に立春の前夜は陰と陽が対立し邪気が生じて災禍をもたらすと考えたところから、邪気を払う意味で行われていました。
中国の風習が日本に!
![]()
| みなさんもご存じのように、日本では「節分」に
豆をまく習慣があります。この習慣は中国で大晦日に 行われていた儀式(追儺(ついな)式)が日本に七世紀の 末頃に伝えられたことが始まりと言われています。 これは、日本でも宮中で大晦日に行われる追儺の儀式と なりました。この儀式は悪鬼や厄神を追い払う儀式では 寺社でも行われるようになり、その当時日本で行われて いた豆まきの行事と結びつき、近世には広く民間に 流布し、全国で数多く行われるようになりました。 それが節分です。 |
 |
豆をまく人は決まっている!?
![]()
もともとは一家の主人や長男の役目で、年男や年女(その年の干支の人。12歳もそうなので、小学校5年生、または6年生にあたりますね!)、厄年の人も豆まきをします。家族のイベントという意味合いも強いので、家族全員でまいてもいいでしょう。
| *豆まきの豆について*
重要なことのひとつは煎り豆を使うということです。 生豆を使った場合、 拾い忘れてしまった豆から芽が出ると よくないことがある、と言われています。 |
 |
豆のまき方を知ろう!
![]()
 |
一般的なまき方は「鬼は外」といいながら
玄関から外に2度まき、次に「福は内」と 2度いいながら家の中にまきます。 「鬼は外」「福は内」の口上は少なくとも 室町時代にはできていたようです。 一般的にはこの後、自分の年齢または 年齢より1つ多く豆を食べたりします。 |
|
そこで… 豆が苦手!そんなに数が食べられない! という方へ そんな方たちにおすすめなのが、「福茶」! 茶碗に豆をいれて熱いお茶をそそぎそれを飲めば、 豆を食べたのと同じだそうです。 |
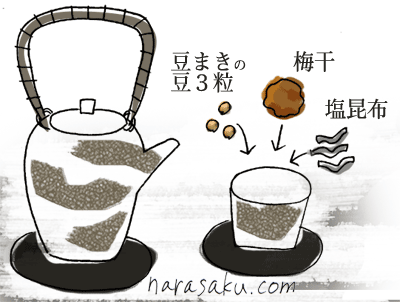 |
豆まき口上「鬼は外、福は内」 について
![]()
|
一般的な豆まきの口上は「鬼は外、福は内」ですが、そう言わないところも数多くあります。これは豆まきの風習が全国に普及していくなかで出来ていったバリエーションではないかと思われます。 その中の一つ、起源がはっきりしているものとして、福島県の二本松地方では「鬼は外」と言わないか又は、「鬼外」と「ハ」の音を抜かします。これは二本松藩の殿様は丹羽氏なので、「鬼は外」と言うと「お丹羽様外」になってしまうからだといいます。 |
 |
 |
節分に食べる恵方巻き
みなさんも聞いたことがあるのではないでしょうか。関西では、巻き寿司をその年の恵方を向いてまるごと無言で食べるとその年は災難をのがれるという風習があります。 巻き寿司を使う理由→「福を巻き込む」 まるごと食べる理由→「縁を切らないために包丁を入れない」 などの理由があるようです。これはもともと、愛知県の方の風習らしいのですが(大阪起源説もあり)1977年に大阪海苔問屋共同組合が、道頓堀で行った節分のイベントをマスコミが取り上げ、早速全国のお寿司屋さんがそれに便乗して全国に広まったということのようです。 なお、恵方(えほう、あきのかた)というのはその年に美しき歳徳神がいる方角です。 |
| ちなみに、2015年の恵方は… |
  |
鬼は「ひいらぎ」と「いわしの頭」が苦手!
![]()
 |
昔から節分の夜に出没すると考えられた鬼ですが、ひいらぎの葉が鬼の目を刺すということで、ひいらぎのあるうちには鬼が来ないといわれていました。また、いわしの頭の異臭が鬼を近づけないことも考えられていました。これらは現代でもひいらぎの小枝にいわしの頭を焼いて刺す「やいかがし」の習慣として残っています。豆まきはこの「やいかがし」で追い払った鬼に追い討ちをかける役目もあったのです。 |
鬼といえば桃太郎
![]()
| 桃太郎は鬼を倒すために、非常に強力な象徴を率いて攻めていきました。まず桃太郎自身が「桃」から生まれていますが、桃は中国古代より悪霊邪気を祓う聖なる植物とされていました。そして、連れているお供が犬・猿・きじですが、これは十二支でいうと、申・酉・戌と対応しており、これは方位に直すと、ちょうど西の方位をカバーしています。西は陰陽道では「硬いもの」つまり金物=剣であり、鬼を倒すのに力強い存在なのです。 |  |
節分の豆知識 より
